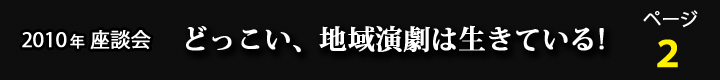蓬莱 合田さんの話で引っかかるのは、ドイツでは行政サイドの支援があるから出来ているんだと聞こえる。そのことには違和感があります。どろがやってきたことはささやかだけど素晴らしいことだと思う。地域の中でどろが消えていく風景が寂しいからこそ続けてくれと観客が言う。そのことと行政の支援とはどう繋がるのか、意見をもらった方がいいかな。
合田 僕は芝居は支援がいると思う。ヨーロッパでは、入場料だけで賄うことは不可能で、贅沢だけれど必要なもの、行政の支援があって当り前という図式が出来上がっている。日本はほとんどの劇団が自力でやっている。やれない事はないが、芸術や文化の恩恵を多くの人が享受するまでには至らない。我々にもほんの少しだが助成があり、それで続けていけることもあるので、社会に貢献しなければならないだろう。効果のことを考えると、助成額はもっと大きくないといけないと思いますね。
三村 行政云々より、我々の劇団は6人からスタートし、だんだん人が減ってきて、今まで関わってくれた人が、職場の関係やら何やらで消えていってしまって、人が増えていかない。若い人が観て、こんな芝居だったら自分もやってみたいと入ってくればいいが、そういうふうにはならない。ああ、自分達の芝居は若者にとって魅力がなく、力が無かったんだと実感する。演劇の意義はといった議論の前に、我々、創る側に責任があるのではないかと、この頃思うんです。
大西 合田さんは先程、さよなら公演をやって、観客からもっと続けてくれと言われて初めて自分達の芝居はこの人たちにとって観たい芝居だったんだ。45年は無駄ではなかったと気付いたと言いました。「神劇まわり舞台」は今年27回目、1年あたり平均2000から2500人が観てくれて、26年続いている。我々はそこに観続けてくれる人が確かにいるんだと改めて気付かされる。そのことはとても大事だし、実はスゴイ事なんです。
蓬莱 姫路で継続的にやっているのはプロデュース・Fさんですが、今の話はどう思いますか。
小林 東京と神戸を比べるのと同じくらい、神戸と姫路は距離があるんです。だから逆にやり易いという気もします。姫路周辺の揖保川町とか神崎町などで地域住民が行政と一緒になって村芝居の様なものを創ろうとしているのを見て、ああこういう小さい行政の方が楽しいものが創れる可能性があるなと思いますね。我々も市制百周年の記念演劇などを依頼され、行政と一緒に創ってきましたが、確かに行政支援は経済的には助けられていると思います。
大西 蓬莱さんは行政からの支援にはあまり乗り気ではないのですか。
蓬莱 ドイツなどヨーロッパではオペラや演劇などが根付いていて、そこに公金を使うことに理解が得られるが、日本では不況対策にもっと金を使えという様な議論が先にたって、単純に論じられないので言わないのです。共同体の村芝居を創るという様な場合はその地域の誰もが待ち望んでいるものだから、そこに公の金を使うことに文句は出ないでしょう。
今泉 欧米諸国と日本との大きな違いは、欧米諸国には学校の教科の中に演劇関係の教科が大体あるんです。音楽や美術と同等に演劇がある。ところが日本では演劇はない。だから一生演劇に触れることなく過ごす人が大勢いる。そういう訳で日本では演劇といえば好きな者が勝手にやっているという意識が世間一般に拡がっている。
蓬莱 僕も神戸市の助成を少しは受けていますが、公平性の原則とか、受ける側の劇団の演劇の方向性とか、色んな問題があるんです。たとえ反社会的であろうと一律に助成するのか、選択と集中でピンポイントに公の金を出すのか、助成をどう捉えるかというのはかなり難しい問題だと思います。
小林 あの、プロデュース・Fは恒常的に助成金をもらっている訳ではないので念のため。ただ私達は姫路市や文化振興財団の職員の方々と日頃から仲良くしていて、色んな情報が入ってきます。時にはしんどい目に合うこともありますがお互い様です。でも、お金出してもらってるからといって、芝居の内容にまで口出しされる様なことであればもらうつもりはありません。
大西 垂水のレバンテホールがネットで自由人会を見つけて一緒に芝居を創りたいと言ってきたんですよね。どういう内容かというと、定年を迎えた人達が何をしたらいいのか分からない。垂水の担当者は街を活性化するためにも何とかしたいと思って連絡を取ってきたらしい。その辺の話をしてもらえますか。
森 垂水の話ですが、老人会とか地域の自治会などに当たっていくと、晩年を迎えた人たちは、残された時間をどう有意義に過ごすかに関心が強く、それを探している人は多い。今、5人に1人は65歳以上なんです。我々が目指すはその人たち。豊かな老後を願っている人たちを観客に取り込んで、有意義な時間を過ごせるような作品を創っていこうと考えています。垂水の場合は、会場費がタダというだけで助成金が出る訳ではありません。ですから、参加者に集まってもらって何回かミーティングを持ち、芝居にしていく。そうすればその人たちが観客になってくれると。このところ、助成金もどんどん減ってきているので、それに代わる行政とのタイアップの方法を兵劇協として考えていければと思います。
蓬莱 先程の街づくりですが、「街づくり」「人づくり」と言った時に、ある種の教育活動やワークショップやシニア劇団といった活動を指しているのだとすれば、多くの若い子たちの劇団は公共性が無いということになる。そういう活動をしていない劇団は社会的にどんな役割を果たしているのかということをうまくすくい取らないと。奉仕活動的な演劇活動をしていないと公共性がない。そういう論理をどう乗り越えるのかということを言っているんです。だから反体制でも行政は金を出すべきだと僕は思うんです。
蓬莱 さて、好きなことをやってると、なかなか言いにくいところがある。それで、違うと言ってしまったんですが、地域性のある芝居をというと、姫路でいえば、姫路城物語をやらなければならないとか、ある種地域に密着したというイメージがありますよね。
小林 姫路は芝居の場所があり人がいる。そういう街でありたいと思うから続けてこられたんだと思います。姫路には「姫路地方文化団体連合協議会」があって、私が芝居を始めた20歳の頃、協議会の十周年の記念事業で「戦後演劇史、美術史、文学史」という、戦争直後からその時までの歴史を紐解いた展示会と年表作りに参加したんです。多くの人に会い、色々な方と知り合えました。今、私たちは芝居をしている。戦前も、戦争中にも芝居をやりたい人がいて、どんな状況下でもやっていた。姫路ってそういう所なんだと思えたから、今も続けられていると思うんです。うちの代表はもう80歳なんですが、学制が新制に代わった時、高校3年生だったんです。昭和23年頃、まだまだ「男女席を同じうせず」といった時代に男女共学になって、学校に演劇部を作ったんです。当時、朝日新聞に「青い山脈」が連載され、これを自分達で芝居にして、公会堂で発表したりして、そこから戦後の姫路のアマチュア劇団がスタートしたんです。今私達はそういうものを手渡されてきています。しかし、次に手渡すことも出来ずに無くなってしまいそう。継続していかなくちゃという責任感に近い気持ちが支えているんです。当時の年表を見ていくと、戦後の姫路の演劇史のなかで、この時ってこんなに輝いていた時代だったんだとか、こうして積み上げてきた時代なんだとわかるんです。だから今、ものすごく低迷していて、劇団員がどんどん減って、家賃が払えなくなりそうで、まあ5年後無くなっているかもしれない。あとの時代の人が、あの時この人たちこんなにしんどかったのに頑張ってやっていたのかと思ってもらえたら。
→次ページへつづく
|